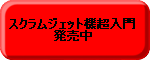|
|
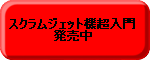
|
第4講 スクラムジェットエンジンの技術課題
「技術課題」と言った場合に、まず「誰にとって」というのを明らかにする必要があります。
例えば、スクラムジェットエンジンの研究開発を世界が一緒になって共同で開発しているわけではなく、各国、各機関が独自に開発を進めており、肝心の部分は秘密にされたままで、他のものが簡単にはその成果を利用することが出来ないからです。
勿論、基礎研究の分野では、インターネットや学会での発表を通じて多くの情報が開示されていますが、それらであっても氷山の一角だと思ったほうがよいでしょう。
試験装置や計測技術も「技術課題」に含めるべきだと考えられます。
高度30kmをマッハ10で飛行している時の空気の流れを地上で作り出すなんて、考えただけでもすごいですよね。
おまけに、その気流をスクラムジェットエンジンの空気取り入れ口で上手く減速しているかとか、減速してそれでもマッハ3くらいある気流の中でちゃんと燃料が燃焼しているかを観察する技術なんかもすごい技術だなということはなんとなく理解できますよね。
技術の成熟度といった観点から最近Technology Readiness Level(TRL)というものが各国、各分野で用いられるようになってきましたが、このTRLのレベルによっても「技術課題」が異なってきます。
つまり、大学の研究室レベルで研究する場合の「技術課題」と、企業が実用化を目指して研究する場合の「技術課題」は異なるわけです。
TRLレベルとしてはかなり下に位置する「スクラムジェットエンジンの成立性」を確認するためだけでも沢山の「技術課題」があります。
日本ではJAXAが超音速燃焼を確認するための飛行実験をオーストラリアの実験場で試みたことがあります。
これが、日本としては最も高いTRLレベルでの試験だったと考えられます。
勿論そこに至るまでに、地上での燃焼試験では角田でマッハ7の条件で、正味推力がプラスになることを確認しています。
他方、TRLレベルで一番下に位置する「アイデア提案」のレベルでの活動も行なわれ、色々なアイデアが検討されています。
そして、実用化の際には、現在は課題としてすら取り上げられていない大気汚染、騒音、耐久性、整備性等現在実用化されているジェットエンジンが抱えている諸問題がさらに超えるべき課題として現れることになります。
このように見てくると、スクラムジェット機の実現は夢物語のように思えるかもしれませんね。
高校生は夢を持つほうがよいでしょうね。
ライト兄弟のように自分たちが初めて空を飛ぶといった栄冠を手に入れることができる可能性があるのですから。
大学3年生レベルを対象とした「理系大学生のためのスクラムジェットエンジン入門」では、この夢を現実のものとするためのロードマップについて述べるつもりですので、余力のある方は御覧下さい。
(MM20111231)
|